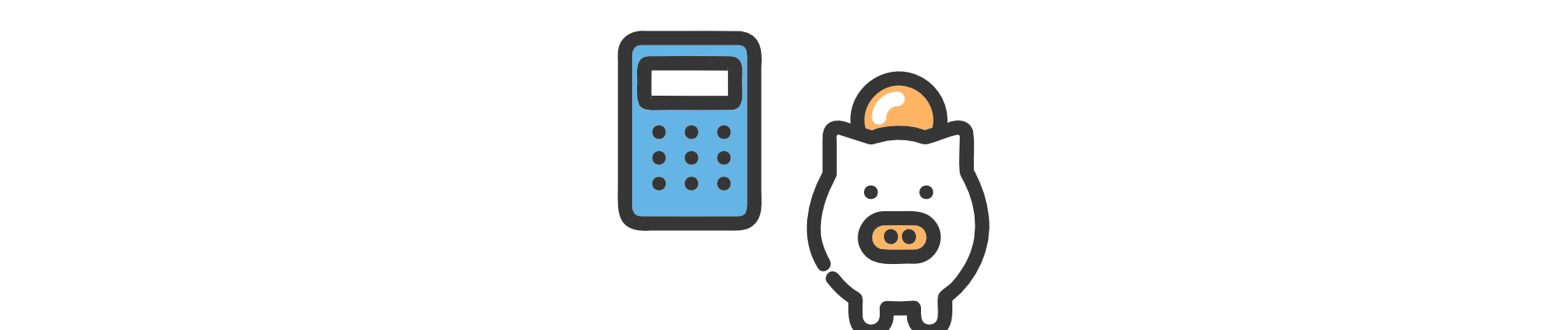採用活動において、給与は候補者が企業を評価する最も重要な要素の一つです。しかし、その影響は応募段階だけでなく、採用後の定着にまで及びます。本記事では、公的データや経営心理学の知見を基に、企業が採用を成功させるための「戦略的な給与設定」について考察します。
「給与レンジ」の科学 – なぜ±20%が基準なのか
給与設定の第一歩は、ターゲット人材の「市場価値」を把握し、それに基づいた「給与レンジ(給与の範囲)」を設けることです。多くの企業で、このレンジは市場価値の中央値を100%とした場合、80%~120%(中央値の±20%)の範囲で設計されます。
市場中央値
±20%の論理的根拠
この「80%~120%」という範囲は、単なる慣習ではなく、人材マネジメント上の合理的な理由に基づいています。
- 80%未満:市場価値を大幅に下回り、競争力がありません。人材の獲得が困難になるだけでなく、既存社員の離職リスクが極めて高まる危険水域です。
- 80%~100%:社員の習熟度や成長を反映させるためのゾーンです。経験の浅い社員は80%に近い位置からスタートし、経験を積み、期待される役割を完全に果たせるようになった段階で100%(市場中央値)に到達するのが理想です。
- 100%~120%:期待を上回る成果を出すハイパフォーマーや、豊富な経験を持つベテランを評価するためのゾーンです。社員の成長に応じて昇給させる余地(昇給余力)を確保し、モチベーションを維持する役割があります。
- 120%以上:市場価値を大幅に上回ります。全社的な給与の公平性を損なう可能性があり、よほど特別なスキルを持つ人材でない限り、慎重な判断が求められます。
つまり、この±20%の幅は、社員の成長と貢献度を給与に反映させ、同時に企業の競争力と内部の公平性を保つための、戦略的なバッファーなのです。
戦略的給与レンジの設定と調整フロー
では、具体的にどのように自社の給与レンジを設計し、調整すればよいのでしょうか。基本的なフローは以下の通りです。
-
1
市場調査の実施
公的統計(賃金構造基本統計調査など)や民間の給与調査データ、競合他社の求人情報から、対象職種の市場価値(中央値)を特定します。
-
2
給与レンジの定義
市場中央値を基に、自社の給与ポリシーに合わせてレンジ(例:80%~120%)を定義します。これにより、職務等級ごとの給与テーブルが完成します。
-
3
個人の位置付け(評価)
候補者や社員の経験・スキル・パフォーマンスを評価し、定義したレンジ内の適切な位置に給与を決定します(例:新人は90%、ハイパフォーマーは110%)。
-
4
定期的な見直し
年に一度など、定期的に市場データを再調査し、給与レンジ自体を更新します。また、個人の評価に応じてレンジ内での昇給を検討します。
給与レンジの高低が応募・採用・定着に与える影響
±20%という幅は決して小さくありません。このレンジの中でどの水準を提示するかは、採用戦略そのものです。提示額の高低は、応募者の数や質、そして採用後の定着率に明確な違いをもたらします。
レンジ低位(80%~95%):若手やポテンシャル層の母集団形成には有効ですが、即戦力を求める場合、経験豊富な候補者からの応募は少なくなります。採用できたとしても、市場価値を認識した段階での早期離職リスクを常に抱えることになります。
レンジ中位(95%~105%):最もバランスの取れた水準です。十分なスキルを持つ候補者からの公正なオファーと受け取られ、安定した応募数と質が期待できます。この層の定着は、給与以外の「動機付け要因」が大きく影響します。
レンジ高位(105%~120%):優秀な人材、特に他社で活躍中のハイパフォーマーや、転職市場にいない「待ち」の候補者を引き抜く力があります。応募の質は非常に高まりますが、採用後はその高い給与に見合うだけの成果が厳しく求められます。定着率は高くなる傾向にあります。
給与だけでは人は辞める – 定着の心理学
ここで改めて重要になるのが、経営心理学者ハーズバーグの「二要因理論」です。
| 衛生要因 (Hygiene Factors) | 動機付け要因 (Motivator Factors) |
|---|---|
|
【満たされないと不満】
|
【満たされると満足】
|
この理論では、給与は「衛生要因」に分類されます。つまり、給与が市場価値より低いと従業員は不満を感じて辞めてしまいますが、高いからといって満足感や仕事への意欲が無限に湧き続けるわけではないのです。給与はあくまで「不満の解消」要因であり、従業員の定着と活躍のためには、仕事の達成感や成長といった「動機付け要因」をいかに提供できるかが鍵となります。
まとめ – 戦略的な給与設定への道筋
採用成功と事業成長を実現するため、企業は給与を多角的に捉え、戦略的に活用する必要があります。
-
市場価値に基づいた「公正な」給与レンジを提示する
データに基づき、自社の業界や地域における客観的な給与相場を把握し、透明性のある形で候補者に提示することが、採用活動の出発点です。 -
給与を「守り」の要素として捉える
適切な給与は、従業員の不満を防ぎ、離職を食い止めるための「守備的な」役割を果たします。これは、定着の最低条件と心得ましょう。 -
真の定着は「動機付け要因」で勝ち取る
他社との人材獲得競争に打ち勝ち、従業員に長く活躍してもらうためには、給与以外の「動機付け要因」が不可欠です。挑戦的な仕事、正当な評価と承認、成長できる環境を整備することが、「攻め」の定着戦略となります。
給与は、採用における「王様」ではなく、全ての土台となる「インフラ」です。強固なインフラを整備した上で、人々が「ここで働きたい」と心から思える魅力的な環境をどう築くか。その視点こそが、これからの時代に企業が持ちべき採用戦略の核心と言えるでしょう。