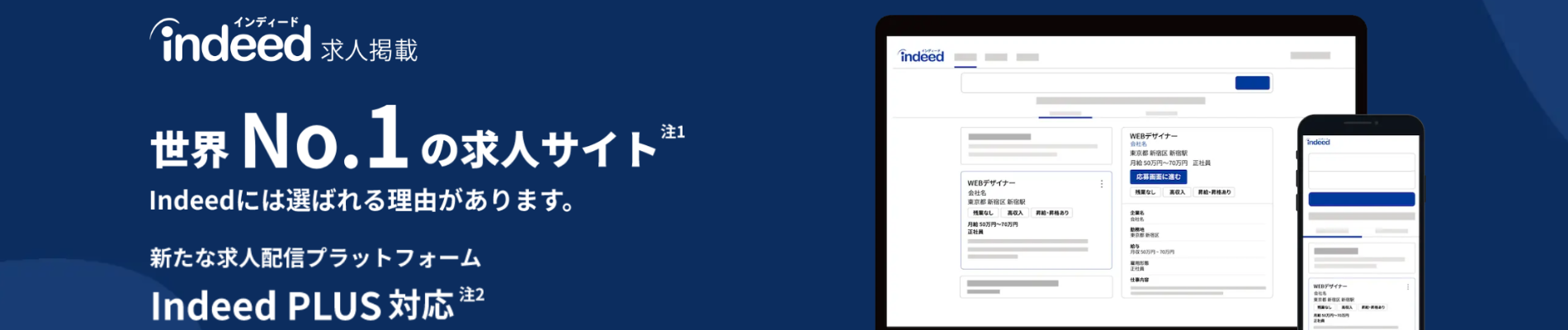求人検索エンジンの巨人、Indeed。多くの企業がその集客力に期待を寄せる一方、近年の採用市場の変化を受け、Indeed自身も大きな転換期を迎えています。本記事では、親会社リクルートホールディングスの最新決算からIndeedの現在地と今後の戦略を読み解き、PPC広告を利用する企業が今、何を意識してこのプラットフォームと向き合うべきかを解説します。
1. 最新決算で見るIndeedの現在地
Indeedの業績は、親会社であるリクルートホールディングスの「HRテクノロジー事業」の決算報告で明らかにされます。最新の2025年3月期通期決算を見ると、いくつかの重要なトレンドが見えてきます。
成長は続くも、市場は冷静化 – 日本市場の「Indeed PLUS」が牽引
コロナ禍後の爆発的な採用需要(いわゆる”グレート・レジグネーション”)が一巡し、世界的に採用市場は落ち着きを取り戻しています。この影響を受け、Indeedの売上成長率も以前よりは緩やかになりました。特に米国市場では、求人件数の減少に伴い、売上収益が前年同期比でマイナスとなる四半期も見られます。
一方で、日本では大きな動きがありました。2024年1月31日に提供開始が発表された「Indeed PLUS」は、その後、提携する大手求人メディアとの連携を順次拡大。調査によれば、2024年後半から本格的なサービス展開と機能拡充が進み、2025年上期には市場での存在感を確固たるものにするための強力なプロモーションが行われています。この日本独自の戦略が功を奏し、国内の売上成長を力強く牽引しています。(参照:リクルート プレスリリース)
決算サマリー(HRテクノロジー事業 2025年3月期)
リクルートホールディングス全体の成長を牽引する中核事業としての地位は揺らいでいません。調整後EBITDAマージンも35%前後と高い収益性を維持しており、採用市場の変動に対応しながらも、安定した経営基盤を築いていることが示されています。
2. データで見るIndeed(HRテクノロジー事業)の成長性
下記のグラフは、Indeedを含むリクルートHRテクノロジー事業の過去数年間の売上収益と、収益性を示す調整後EBITDAマージンの推移です。コロナ禍以降の急成長と、その後の市場の冷静化、そして依然として高い収益性を維持している様子が見て取れます。
※2024年3月期より会計基準がIFRS第17号適用のため、売上収益の算出方法が変更されていますが、ここでは傾向を把握するため継続性のある数値をグラフ化しています。
3. Indeedが描く未来 – 「採用プラットフォーム」への進化
Indeedは、もはや単なる「求人広告を載せる場所」ではありません。決算説明会や公式発表から見えるのは、採用プロセス全体を効率化する「総合採用プラットフォーム」への進化です。
戦略1:課金モデルの多様化と成果報酬へのシフト
従来のクリック課金(PPC)モデルに加え、応募課金(PPA – Pay Per Application)や、一部で試験導入が進む採用課金(PPH – Pay Per Hire)へと課金体系を多様化させています。これは、企業の採用成果により近い指標で課金することで、広告主の費用対効果を高め、リスクを低減させる狙いがあります。
戦略2:採用業務の包括的支援
応募者管理(ATS)機能の強化や、AIによる面接予約の自動化など、これまで人事担当者が手作業で行っていた業務をIndeed上で完結させるための機能拡充を急いでいます。これにより、特に採用専門の部署を持たない中小企業でも、効率的に採用活動を進められる環境を整えようとしています。
戦略3:AI活用と「求人の質」の徹底追求
IndeedはAIによるマッチング精度向上に力を入れると同時に、それ以上に「求人情報の質と信頼性」の担保に莫大なリソースを投下しています。かつては、一部の人材紹介会社などによる質の低い求人やスパム的な投稿が問題視されることもありました。
これに対し、近年Indeedは不適切な求人を自動的・手動で徹底的に排除し、悪質なアカウントはBAN(利用停止)措置を取るなど、厳格な品質管理を本格化させています。これは、求職者が安心して利用できるプラットフォームを維持し、利用体験を向上させることが、結果として優良な広告主と真剣な求職者を結びつける最善の策であるという強い意志の表れです。
4. 競合との違いとIndeedのポジショニング
採用チャネルが多様化する中で、Indeedの立ち位置を正しく理解することが重要です。
| 特徴 | Indeed | 大手求人サイト(リクナビ等) | |
|---|---|---|---|
| ビジネスモデル | 求人検索エンジン (クローリング+直接投稿) |
求人広告媒体 (掲載課金型) |
ビジネス特化型SNS |
| 強み | 圧倒的な求人情報量とトラフィック。運用型広告による柔軟なコスト管理。 | ブランド力と信頼性。新卒採用や若手層に強い。手厚いサポート。 | ハイクラス・専門職に強い。潜在層へのダイレクトアプローチ(スカウト)。 |
| 課金形態 | クリック課金、応募課金など運用型が中心。 | 掲載期間・枠に応じた固定料金が中心。 | スカウト送信、求人掲載など月額・年額課金が中心。 |
Indeedの最大の強みは、あらゆる求人を集約する「網羅性」と、広告主が自ら運用をコントロールできる「柔軟性」にあります。一方で、その自由度の高さゆえに、効果を出すためには相応の知識と工夫が求められるプラットフォームとも言えます。
5. 【広告主必見】これからのIndeedとの付き合い方
Indeedの戦略転換は、広告主である私たちに新しい向き合い方を求めています。これからの採用競争を勝ち抜くために、以下の点を強く意識しましょう。
「出稿」から「運用」へ – 受け身からの脱却
もはや「求人票を載せておけば応募が来る」という考え方は通用しません。クリック単価(CPC)、応募単価(CPA)、採用単価(CPH)といった指標を日々確認し、「なぜ応募に至らないのか」「どのキーワードが有効か」を分析・改善し続ける「運用」の視点が不可欠です。Indeedを、自社の採用活動を最適化するためのパートナーとして能動的に使いこなす意識が求められます。
求人票こそが最強の武器
IndeedのAIは、求職者の検索意図や行動履歴を基に、最適な求人票を表示します。つまり、求職者が本当に知りたい情報(具体的な仕事内容、給与、働き方、職場の雰囲気など)が具体的に書かれた「質の高い求人票」は、AIによって評価され、結果的に少ない広告費でより多くのターゲットに届きます。求人票の質を高めることこそ、最も費用対効果の高いIndeed運用術です。
多様化する課金モデルを使いこなす
クリック課金(PPC)が最適とは限りません。例えば、応募の質に課題がある職種ではPPCで広く母集団を形成しつつ求人票を改善し、ある程度応募が見込める職種では応募課金(PPA)に切り替えて無駄なクリック費用を抑制する、といった戦略的な判断が必要です。自社の採用フェーズや職種特性に合わせて、最適な課金モデルを選択・組み合わせることで、採用コストを大きく改善できる可能性があります。