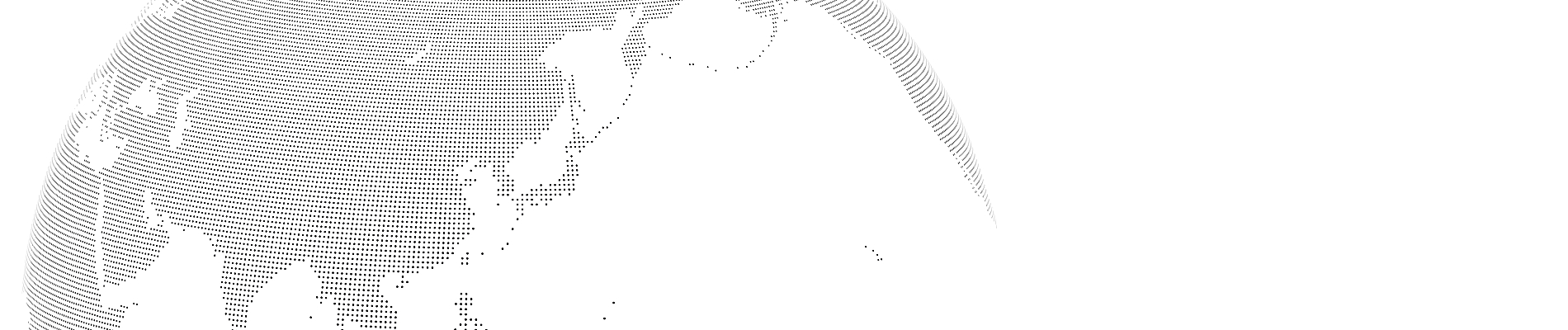深刻な労働力不足に直面する日本にとって、外国人材の受け入れ拡大はもはや避けて通れない。その未来像は、移民大国・米国の現状に映し出される。経済を牽引する「活力」と、社会に横たわる「ジレンマ」。日本企業と社会は、この現実から何を学び、備えるべきか。
1. 賃金格差と労働者の流れ
国境を越える人の移動、その根底には圧倒的な経済格差が存在する。日本の労働市場が、アジアの近隣諸国からどのように見えているか。OECDや各種調査に基づく平均月収の比較が、その引力を物語る。
| 国名 | 平均月収(推計・円換算) |
|---|---|
| 日本 | 約380,000円 |
| ベトナム | 約45,000円 |
| フィリピン | 約40,000円 |
| ネパール | 約25,000円 |
この数倍から十数倍にもなる賃金差が、日本への就労を目指す強い動機となっている。一方で、世界の労働者の流れは、より高い報酬と機会を求める巨大な潮流だ。国連の報告によれば、メキシコから米国、インドからUAE、中国から米国といった巨大な移住ルート(マイグレーション・コリドー)が存在し、日本もまた、東南アジアからの人材獲得において、韓国や台湾、中東諸国といった国々と激しい競争を繰り広げている。
2. 議論の前提 – 「正規移民」と「不法移民」の区別
本稿で論じる「移民」とは、国の法制度に基づき、在留資格を正式に取得して居住・就労する「正規の移民・外国人労働者」を指す。これは、法律に基づかない形で滞在する「不法移民(または不法残留者)」とは明確に区別されるべきである。
例えば、しばしば移民問題が議論される米国では、外国生まれの人口約4,500万人のうち、許可なく滞在している「不法移民」は1,000万人強と推定されている。つまり、全体の8割近くは合法的な手続きを経た正規の移民であり、本稿で後述する米国の経済的活力やイノベーションは、主にこの正規移民の力によって支えられている。
日本においても、出入国在留管理庁によれば、不法残留者の数は約8万人(2024年初頭時点)であり、これは在留外国人全体(約340万人)の約2.4%に過ぎない。本稿は、不法移民の増加をシミュレートするものではなく、日本が国家として、どのようなルールで正規の外国人材を受け入れていくか、そして企業はその未来にどう備えるべきかを論じるものである。
3. 移民大国アメリカとの「差」と日本の進むべき道
正規の外国人材の受け入れに対する日米のスタンスの差は、数字の上で明確に現れている。総人口に占める外国生まれの住民の割合は、米国が約15%に達するのに対し、日本は約2.5%に過ぎない。この差はどこから生まれるのか。
なぜ米国は「選ばれる」のか
米国の魅力は、単なる経済的な機会だけではない。「アメリカン・ドリーム」に象徴される成功への期待感、世界最高峰の大学群、そして何よりも、移民とその子供たちが社会のあらゆる層で活躍しているという事実そのものが、強力な磁力となっている。フォーチュン500企業のうち45%近くが移民またはその子供によって設立されたという事実は、彼らが単なる労働力ではなく、イノベーションの源泉であることを示している。永住権や市民権への道筋が比較的明確であることも、長期的な人生設計を考える上で大きな魅力だ。
先進国で唯一「労働力が増え続ける国」
この正規移民の力が、米国の人口動態に決定的な違いをもたらしている。OECDの予測では、多くの先進国が生産年齢人口の減少に苦しむ中、米国は今後も労働力人口の増加が見込まれる数少ない国である。移民が経済のダイナミズムと若さを維持し、国家の成長を支えている。対する日本は、世界で最も速いスピードで人口減少と高齢化が進行しており、このままでは経済規模の縮小は避けられない。
日本が目指すべきは「移民から選ばれる国」
この状況を打開するためには、日本も早晩、「移民から選ばれる国」へと舵を切らざるを得ない可能性が高い。それは単に門戸を開くことではない。世界中の人材獲得競争の中で、日本という国、そして日本の企業が、働く場所として魅力的であると認識されるための、国家レベルでのブランディングと、個社レベルでの努力が求められる。
企業に求められる「共生」への組織改革
その未来において、外国人材が企業の本当の「戦力」となるためには、企業は今から組織のあり方を根本的に見直す必要がある。
第一に、評価とキャリアパスの公平性だ。国籍を理由に昇進や昇格に「見えない天井」が存在するような企業は、優秀な人材からすぐに見切りをつけられる。日本人社員と全く同じ基準で評価し、同様のキャリアアップの機会を提供することが大前提となる。
第二に、多様性を受容するマネジメントへの変革である。これまでの「言わなくても分かる」といった高コンテクストな日本のコミュニケーションは、外国人材には通用しない。管理職は、異文化を理解し、明確な言葉で指示を出し、多様な価値観を持つチームをまとめる新しいリーダーシップを身につける必要がある。
最後に、生活インフラとしての企業支援だ。住居の確保、子供の教育、医療機関での通訳サポートなど、仕事以外の生活面での困難は、彼らのパフォーマンスに直接影響する。優れた企業は、彼らにとっての「第二の家族」ともいえるような手厚いサポートを提供することで、エンゲージメントを高め、長期的な定着を勝ち取っていくだろう。