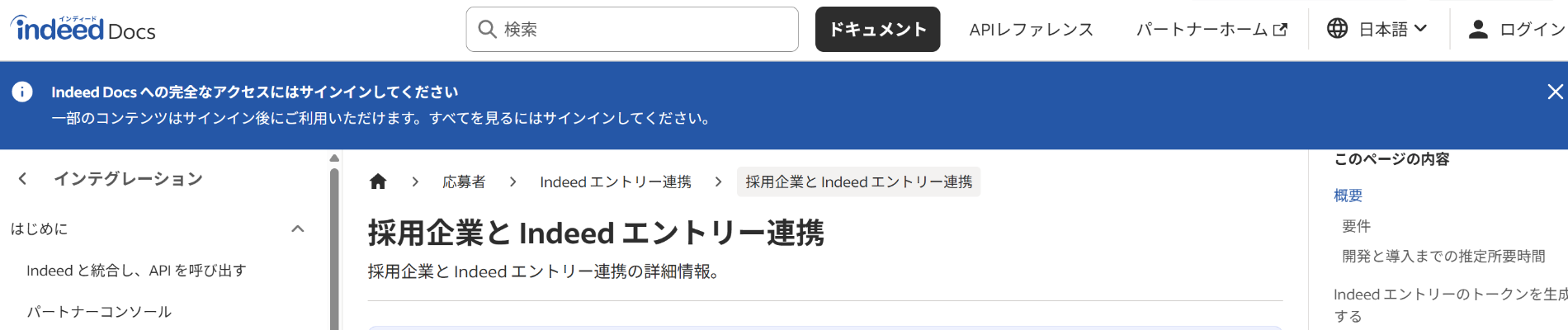「最近、Indeedから自社サイトへの応募が減った…?」多くの採用担当者が感じているこの変化。その裏には、Indeedが静かに、しかし着実に進めてきた大きな戦略転換があります。それが「Indeed Apply(インディード・アプライ)の事実上の必須化」です。
かつて「求人版Google」とも呼ばれた検索エンジンは、今や応募から管理までを内包する巨大な独自経済圏を築こうとしています。この変化は、採用企業にとって何を意味するのか。本記事では、Indeedの狙いを深掘りし、企業が直面するデメリットと、これから取るべき具体的な対策を徹底解説します。
何が変わったのか?「Indeed Apply必須化」の概要
これまでのIndeedと、現在のIndeedでは、求職者の応募フローが根本的に変わりました。
【以前】リダイレクト方式
【現在】プラットフォーム完結型
特に有料掲載(スポンサー求人)において、求職者はIndeedのプラットフォーム内で応募を完結させる「Indeed Apply」、またはIndeedとAPI連携した採用管理システム(ATS)を経由した応募が基本となりました。これにより、企業が自社の採用サイトへ応募者を直接誘導することが、原則としてできなくなったのです。
Indeedの野望 – なぜ「囲い込み」戦略へと舵を切ったのか?
この大きな変化の背景には、単なる利便性向上だけではない、Indeedの明確な戦略があります。
検索エンジンから、完全なプラットフォームへ
創業当初のIndeedは、世界中の求人情報を集約して見せる「求人検索エンジン」でした。しかし今回の変更は、その立ち位置を捨て、ユーザー(企業と求職者)を自社サービス内に留まらせ、応募から採用管理までを一気通貫で提供する「採用プラットフォーム」へと完全に移行する意思表示です。
独自の「Indeed経済圏」の確立
なぜプラットフォーム化を目指すのか。最大の目的は、応募フローを掌握することによる「データ」の独占です。
- 応募データの活用:どのような人が、どのような求人に応募するのかという膨大なデータを収集・分析し、マッチングアルゴリズムを強化。競合に対する優位性を確立します。
- 新たな収益源の創出:収集したデータを基に、企業向けの高度な分析ツールや、より高機能な採用管理サービスを有料で提供するなど、広告以外の収益源を確保します。
- ユーザーのロックイン:Indeed内で履歴書を管理し、応募履歴が蓄積されていくことで、求職者は他のプラットフォームに乗り換えにくくなります。企業側もIndeedのシステムに最適化することで、依存度が高まります。
つまり、Indeedは自社プラットフォームをあらゆる採用活動の中心に据え、そこから生まれる利益を最大化する「経済圏」を築こうとしているのです。
企業が直面するデメリットと新たな課題
このIndeedの戦略は、採用企業にとって看過できないいくつかのデメリットをもたらします。
-
ブランド体験の機会損失
自社の採用サイトへ誘導できないため、デザインやコンテンツを通じて企業の文化・理念・ビジョンといった「世界観」を伝える機会が失われます。候補者は「Indeedで応募した」という意識が強くなり、企業へのエンゲージメント(愛着心)が醸成されにくくなります。
-
応募の「質」の低下懸念
Indeed Applyは数クリックで応募できるため、手軽さから「とりあえず応募」「深く考えず応募」といった、志望度の低い候補者が増加する可能性があります。結果として、書類選考や面接の工数が増大する懸念があります。
-
候補者データの分断と管理の煩雑化
応募者情報がIndeedのシステムに集約されるため、自社で運用している採用データベースとの連携が取れず、候補者情報が一元管理できなくなる恐れがあります。複数のシステムを見なければならず、管理が煩雑化します。
-
採用管理システム(ATS)導入への圧力
Indeedと連携していない独自の採用システムを使っている場合、スムーズな応募者管理のために、Indeedが提携するATSへの乗り換えを検討せざるを得なくなる可能性があります。これは、新たなシステム導入コストに繋がります。
これからの採用戦略 – 企業はどう向き合うべきか?
この大きな変化に対し、企業はただ受け入れるだけでなく、戦略的に向き合っていく必要があります。
今後の採用戦略 3つのポイント
1. Indeedとの付き合い方を再定義する
Indeedを有料で利用する場合、それは「Indeed Apply」というルールの上で戦うことを意味します。応募者のサイト誘導ができない前提で、Indeedの求人情報内でいかに簡潔に魅力を伝えるか、そして応募後の連絡をいかに迅速に行うか、という運用体制の見直しが求められます。
2. 自社採用サイトの「価値」を再定義する
Indeedを「認知獲得・応募の入口」と割り切る一方、自社の採用サイトは「企業文化の深い理解と、入社意欲の醸成の場」として、その役割をより明確に強化する必要があります。Indeedの求人情報内に採用サイトへのリンクを記載し、「より詳しい情報はこちら」と能動的な候補者を誘導する導線を設計しましょう。
3. 「脱・Indeed依存」採用チャネルの多様化
最も重要なのが、Indeedへの過度な依存から脱却することです。今回の変更は、一企業のプラットフォーム戦略に自社の採用活動が大きく左右されるリスクを浮き彫りにしました。今後は、Googleしごと検索(Indexing APIでの連携が望ましい)、SNSを活用したダイレクトリクルーティング、リファラル(社員紹介)採用、人材紹介など、複数の採用チャネルをバランス良く組み合わせる「採用ポートフォリオ」の構築が、これまで以上に重要になります。
Indeedのプラットフォーム化は、もはや止められない大きな潮流です。この変化を正しく理解し、適応しつつも、自社の採用力を一つのプラットフォームに依存させない。そんなしたたかな戦略を持つ企業こそが、これからの人材獲得競争を勝ち抜いていくことができるでしょう。