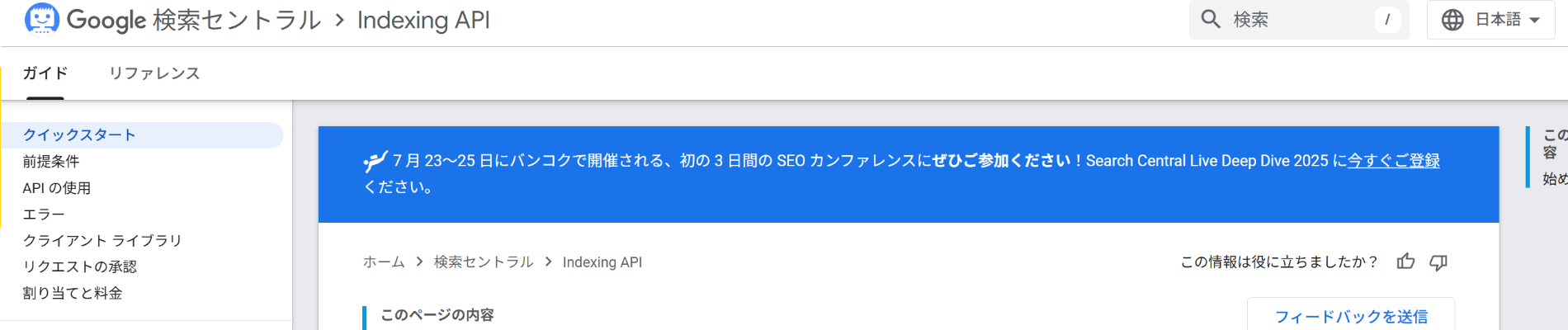今や採用活動の主流となった「Googleしごと検索」。自社の求人情報をこのプラットフォームに掲載することは、優秀な人材を獲得するための必須条件です。しかし、その連携方法には「サイトマップ」と「Indexing API」の2種類があり、どちらを選ぶべきか悩む担当者も少なくありません。
本記事では、これら2つの連携方法の根本的な動作の違いから、SEOへの影響、そして具体的な実装ステップまでを徹底的に解説します。自社に最適な方法を選び、採用効果を最大化するための一助となれば幸いです。
Googleしごと検索の基本 – すべては「構造化データ」から始まる
サイトマップとAPI、どちらの連携方法を選ぶにせよ、絶対に必要な共通の作業があります。それが「JobPosting構造化データ」のマークアップです。
これは、求人ページのHTML内に、職種名、給与、勤務地、雇用形態といった求人情報を、Googleのロボットが理解できる形式で記述することです。この構造化データがなければ、Googleはあなたのページを「求人情報」として認識できず、Googleしごと検索に掲載されることはありません。
<script type="application/ld+json">
{
"@context" : "https://schema.org/",
"@type" : "JobPosting",
"title" : "ソフトウェアエンジニア",
"description" : "<p>革新的なウェブアプリケーションの開発をお任せします...</p>",
"datePosted" : "2025-06-28",
"validThrough" : "2025-07-28T23:59:59",
"employmentType" : "FULL_TIME",
"hiringOrganization" : {
"@type" : "Organization",
"name" : "株式会社サンプルテック",
"sameAs" : "https://www.sample-tech.co.jp",
"logo" : "https://www.sample-tech.co.jp/images/logo.png"
},
"jobLocation": {
"@type": "Place",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"streetAddress": "丸の内1-1-1",
"addressLocality": "千代田区",
"addressRegion": "東京都",
"postalCode": "100-0005",
"addressCountry": "JP"
}
},
"baseSalary": {
"@type": "MonetaryAmount",
"currency": "JPY",
"value": {
"@type": "QuantitativeValue",
"minValue": 5000000,
"maxValue": 8000000,
"unitText": "YEAR"
}
}
}
</script>このマークアップが完了して初めて、サイトマップかAPIか、という次のステップに進むことができます。
2つの連携方法 -「サイトマップ」と「Indexing API」の動作の違い
構造化データを実装したら、そのページの存在をGoogleに伝える必要があります。その方法が「サイトマップ」と「Indexing API」です。両者の違いを理解するために、サイトマップを「定期巡回バス」、Indexing APIを「タクシー(特急便)」に例えると分かりやすいでしょう。
| サイトマップ連携 (定期巡回バス) | Indexing API連携 (タクシー/特急便) | |
|---|---|---|
| 動作の仕組み | Googleのクローラーが定期的にサイトマップを読みに来て、更新情報を発見する(プル型)。 | 求人情報の変更時に、自社サーバーからGoogleへ即座に「更新した」と通知する(プッシュ型)。 |
| 反映速度 | 遅い(数日〜1週間以上かかることも)。Googleの巡回タイミングに依存する。 | 非常に速い(数分〜数時間)。リアルタイムに近い。 |
| 情報の鮮度 | 低い。募集終了した求人が残りやすく、ユーザー体験を損なう可能性がある。 | 高い。募集終了を即座に伝えられるため、常に最新の状態を保てる。 |
| 実装難易度 | 比較的容易。XMLサイトマップを作成し、Search Consoleから送信するだけ。 | 高い。GCP設定、サービスアカウント作成、APIリクエストを送信するプログラミングが必要。 |
| 向いている用途 | 求人の更新頻度が低いサイト、手軽に始めたい場合。 | 求人数が多く更新頻度が高いサイト(求人メディア等)、情報の鮮度を最重要視する場合。 |
SEOへの影響 – どちらが「有利」なのか?
Googleの使命は、ユーザーに最も関連性が高く、正確で、新鮮な情報を提供することです。この観点から見ると、どちらがSEOに有利かは明らかです。
結論から言うと、Indexing APIが圧倒的に有利です。
求人情報は「鮮度」が命です。募集が終了した求人がいつまでも検索結果に残っている状態(サイトマップ連携で起こりがち)は、ユーザー体験を著しく損ないます。これはGoogleが最も嫌うことであり、サイト全体の評価を下げる要因にもなり得ます。
一方、Indexing APIを使えば、募集終了を即座にGoogleに通知し、検索結果から削除を促すことができます。常に最新で正確な情報を提供し続けるサイトは、Googleから「質の高い情報源」として認識され、結果として検索結果での表示順位や表示機会において優遇される可能性が高まります。
短期的な実装コストはサイトマップの方が低いですが、長期的な採用効果とSEOの観点からは、Indexing APIを目指すべきと言えるでしょう。
実装へのロードマップ – 具体的な作業ステップ
それでは、各連携方法の具体的な実装手順を見ていきましょう。
方法1:サイトマップ連携の実装ステップ
- JobPosting構造化データの実装:(前述の通り、これは必須です)
- 求人専用サイトマップの作成:求人情報ページのURLのみをリストアップしたXMLサイトマップ(例:sitemap-jobs.xml)を作成します。
- Google Search Consoleへの登録:作成したサイトマップをSearch Consoleにログインして、「サイトマップ」セクションから送信します。
- 定期的な更新:求人ページを追加・削除した際は、サイトマップも更新して再送信(または自動更新)する必要があります。 ol>
- JobPosting構造化データの実装:(同様に必須です)
- Google Cloud Platform (GCP) の設定:
- GCPでプロジェクトを作成し、「Indexing API」を有効化します。
- APIを利用するための「サービスアカウント」を作成し、認証情報となるJSONキーファイルをダウンロードします。
- Search Consoleでの所有権確認:
- ダウンロードしたJSONキーに記載されているサービスアカウントのメールアドレスを、Search Consoleでサイトの「所有者」として追加します。
- APIリクエストプログラムの開発:
- 求人情報を「追加・更新」した際、または「削除」した際に、GoogleのAPIエンドポイントに対してHTTPリクエストを送信するプログラムをサーバーサイドで開発します。
- 例えば、新しい求人ページを公開した際には、そのページのURLを通知します。
方法2:Indexing API連携の実装ステップ
まとめ:自社に最適な連携方法の選び方
サイトマップ連携とIndexing API連携、それぞれの特性を理解した上で、自社の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
こんな企業はまず「サイトマップ連携」から
エンジニアリングリソースが限られており、まずは手軽に始めたい場合や、求人の更新頻度が月に数件程度と低い場合には、サイトマップ連携が現実的な選択肢です。ただし、情報の反映に時間がかかるデメリットは理解しておく必要があります。
こんな企業は「Indexing API」を目指すべき
求人数が多く更新頻度が非常に高い求人メディアや大手企業の採用サイト、あるいは採用における競争が激しく、情報の鮮度を最重要視する企業は、Indexing APIの導入を強く推奨します。初期投資はかかりますが、それに見合うSEO効果とユーザー体験の向上が期待できます。
Googleしごと検索を最大限に活用するには、技術的な仕組みを正しく理解し、自社の戦略に合った連携方法を選択することが成功への第一歩となります。