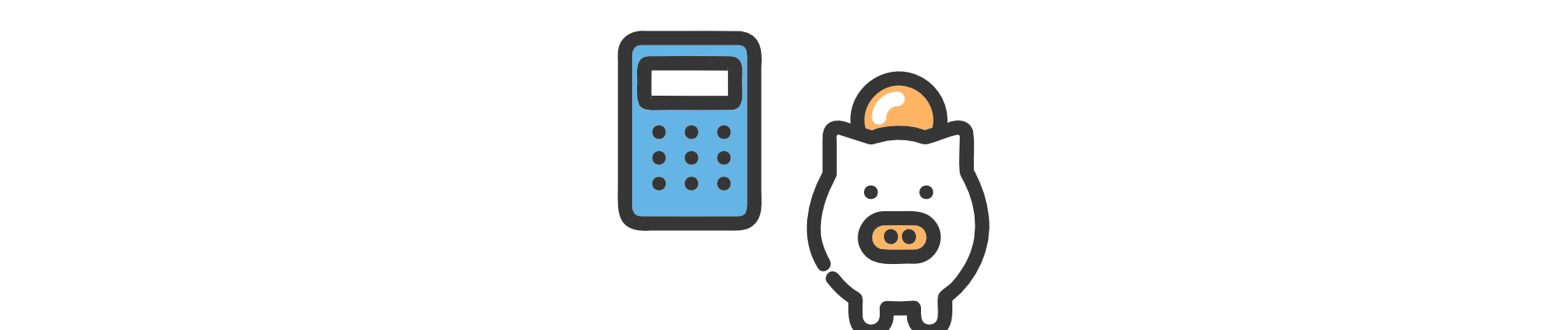「大卒も高卒も、新卒の応募が全く来ない」「採用コストばかりが膨れ上がり、成果に繋がらない」 多くの中小企業が、深刻な新卒採用難に直面しています。これは単なる景気の問題ではなく、日本の労働人口の変化と、学生の価値観の変容という、より根深い構造的な課題です。
この記事では、まず公的な調査データを基に、新卒採用にかかるコストや、学生がどのような企業を求めているのかという「厳しい現実」を直視します。その上で、知名度や待遇で大企業に劣る中小企業が、この人材獲得競争をどう戦い抜くべきか、具体的な選択肢と戦略を提示します。
データで見る新卒採用の現実 – なぜ調査によって金額が違うのか?
新卒採用のコストについて調べると、様々な金額が出てきて混乱することがあります。その理由は、「採用コスト」の定義が調査によって異なるためです。誤解を避けるため、まずその背景を理解しましょう。
- 外部コスト: 求人広告費、合同説明会への出展料、人材紹介会社への成功報酬、パンフレット等の制作費など、社外に支払う費用。
- 内部コスト: 採用担当者の人件費、面接官の時間、リファラル採用の報奨金、交通費など、社内で発生する費用。
調査によって、外部コストのみを集計している場合と、内部コストまで含めて算出している場合があるため、金額に幅が生まれます。
大卒採用のコスト – 100万円超えも視野に
大卒採用は、ナビサイトへの掲載や大規模なイベント出展など、多額の外部コストがかかるのが特徴です。
求人広告費やイベント出展費が主。前年の45.0万円から大幅に上昇しており、競争激化が伺える。非上場企業(57.5万円)の方が上場企業(49.0万円)より高い傾向にあるのは、ブランド力で劣る分、広告費を多くかける必要があるためと考えられる。
広告費などの外部コストに加え、担当者の人件費など内部コストも含めた、より包括的な採用単価の相場。採用活動全体の総費用をリアルに反映した数値と言える。
出典:マイナビ「2024年卒 企業新卒採用活動調査」、および各種民間調査データを基に作成
高卒採用のコスト – 金額だけでは見えない実情
高卒採用は、ハローワークや学校との連携が中心のため、外部コストは比較的低い傾向にありますが、その分、内部コスト(人件費)の比重が高まります。
高卒専門の求人サイト利用費などが主。大卒に比べると安価だが、学校との関係性が築けていない企業が利用するケースが多く、コストをかけても採用に至らないリスクもある。
これは一人当たり単価ではなく、ある調査での「企業が一年間で高卒採用にかけた費用の総額」の試算。この費用の多くは、先生方との関係構築や職場見学の対応といった、担当者の人件費(内部コスト)が占めると考えられる。
出典:各種民間調査データを基に作成
【結論】結局、新卒1名あたりの採用コストは?
様々なデータを総合すると、大卒採用における一人当たりのコストは、
採用活動にかかる総費用として
を一つの目安として見ておくのが現実的です。
※高卒採用は外部費用こそ低いものの、学校との関係構築にかかる人件費(内部コスト)が成果を左右する重要な要素となります。
なぜ大企業や公務員が選ばれるのか?
では、今の学生はどのような企業・職業を求めているのでしょうか。各種の人気企業ランキングからは、明確な傾向が読み取れます。
大卒に人気の企業 – 「安定」と「ブランド」への信頼
2025年卒の大学生を対象とした就職人気企業ランキングでは、業界を問わず、各業界を代表する大手企業が上位を占めています。具体的には、総合商社、金融、大手メーカー、インフラ企業などです。また、近年ではNTTデータグループやSCSKといった大手IT企業の人気も非常に高まっています。
ここから見えるのは、学生が「安定した経営基盤」「充実した福利厚生」「確立されたブランドイメージ」といった要素を重視しているという事実です。これは、将来に対する漠然とした不安の裏返しとも言えます。
高卒に人気の企業・職業 – 「安定」と「専門性」
高校生の就職希望先も、「公務員」が常に上位にランクインしており、安定志向の強さが伺えます。それに加え、「製造・ものづくり」「建設・建築」「情報通信(IT)」といった、手に職をつけられる専門性の高い業界も人気です。これは、自らのスキルで将来の安定を確保したいという現実的な思考の表れでしょう。
結論として、大卒・高卒ともに、一部の特異な人気企業を除けば、やはり知名度と安定性で勝る「大企業」や「公務員」に人気が集中しているのが現状です。この現実を踏まえると、中小企業が同じ土俵で戦うのは極めて困難と言わざるを得ません。
中小企業が「選ばれる」ための3つの生存戦略
大企業と同じ戦い方をしても勝ち目はありません。中小企業は、限られたリソースの中で、独自の価値を的確に届ける戦略が必要です。
戦略1:採用チャネルの転換
大規模な合同説明会のような「マス」向けの施策から、自社に合う可能性の高い層に直接アプローチする「ニッチ」な手法に切り替えます。例えば、地元の工業高校や大学の研究室との連携強化、逆求人型のスカウトサービス(ダイレクトリクルーティング)の活用などが挙げられます。
戦略2:「等身大の魅力」の言語化
大手にはない中小企業ならではの魅力を掘り起こし、求職者に伝わる言葉で発信します。「社長との距離が近い」「若いうちから裁量権が大きい」「事業全体を見渡せる」といった点を、具体的な社員の声やエピソードを交えて採用サイトやSNSで伝え、共感を呼びます。
戦略3:採用ターゲットの再定義
「新卒」という枠に固執せず、視野を広げることも重要です。例えば、社会人経験が浅い「第二新卒」や、スキルを持つ「既卒者」、あるいは地元志向の強い地方学生や、実践的なスキルを身につけた「専門学校生」なども、貴重な人材となり得ます。自社の事業や文化に本当に合うのは誰か、ターゲット像を再定義します。
まとめ – 「戦う場所」を変える勇気
データが示す通り、中小企業の新卒採用は、コスト面でも競争環境の面でも、非常に厳しい状況にあります。この状況下で成果を出すためには、大企業を模倣するのではなく、自社の置かれた状況を冷静に分析し、「戦う場所」と「戦い方」を意図的に変える勇気が必要です。
マス広告で知名度を競うのではなく、一人の高校の先生との信頼関係を築くこと。抽象的な福利厚生を並べるのではなく、一人の若手社員が成長した物語を語ること。そうした地道で誠実な活動こそが、最終的に会社の未来を担う、かけがえのない人材との出会いに繋がります。