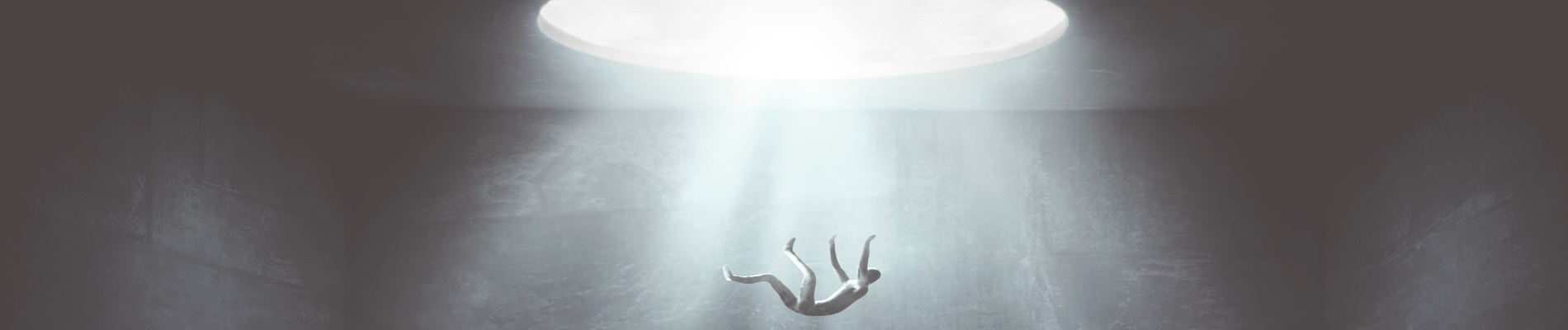「最近、人材派遣会社の倒産が増えていると聞くけど、なぜだろう?」
「人材採用のプロである派遣会社が、なぜ人手不足で苦しむのか?」
長引く人手不足は、多くの業界・企業に深刻な影響を与えています。その中でも、企業と人材をマッチングさせる役割を担うはずの人材派遣会社が、近年、倒産件数を増やしているという事実は、日本の採用市場の現状を象徴しています。
本記事では、この人材派遣会社の倒産増加の背景を、客観的なデータに基づいて深掘りします。人手を集められない「採用難」の現実、人材確保のための「採用コストの高騰」、そして「薄利多売」のビジネスモデルが抱える構造的な課題を考察。プロであるはずの派遣会社が直面する困難を通じて、現代の採用市場の厳しさを浮き彫りにします。
これは、人材派遣業界が直面する大きな課題の序章にすぎません。次回の記事では、これらの課題を乗り越え、持続可能なビジネスモデルを確立するための、より具体的な戦略と、各社の成功事例に深く踏み込んでいきます。
増加する人材派遣会社の倒産現状と推移
東京商工リサーチや帝国データバンクの調査(※1)によると、近年、人材派遣業における倒産件数は増加傾向にあり、特に「人手不足」を直接の原因とする倒産が目立っています。
上記グラフが示す通り、人材派遣業の倒産件数は、2020年代に入り特に顕著な増加傾向を見せています。これは、景気変動だけでなく、構造的な問題が背景にあることを示唆しています。
※1:東京商工リサーチ、帝国データバンクの「人手不足倒産」関連調査、および「倒産月報」などの公表データに基づく記述。正確な数値は各調査機関の最新発表を参照してください。
倒産を招く構造的要因 – 人材確保・コスト・利益
人材派遣会社の倒産が増加している背景には、主に「人材確保の困難さ」「採用コストの高騰」「薄利多売のビジネスモデル」という3つの構造的要因が複合的に絡み合っています。
1. 人材確保の困難さ
日本全体での少子高齢化、特に若年層の労働力人口減少は、派遣登録者数の減少に直結します。人材派遣業は、帝国データバンクの調査(※2)で人手不足を感じる企業の割合が常に高い水準にあり、人手不足の業種トップクラスに位置しています。
求職者は、派遣という働き方に「期間の定め」や「不安定さ」を感じることもあり、より安定した直接雇用や、柔軟な働き方(リモートワーク、副業)を求める傾向が強まっています。
2. 採用コストの高騰
Indeedや求人ボックスなどの運用型広告では、人材獲得競争の激化によりクリック単価(CPC)が高騰しています。また、ダイレクトリクルーティングでのスカウトも飽和状態となり、質の高い人材を獲得するための費用が増大しています。
人材コンサルタントや採用担当者の人件費も、市場価値の上昇に伴い増加傾向にあります。優秀な人材を確保するための競争は、派遣会社自身の採用にも影響を与えます。
人材派遣会社の販促費は、近年、採用競争の激化に伴い増加の一途をたどっています。各社の決算情報(※3)から推計すると、売上高に占める販促費の割合は、特に人手不足が加速した過去数年間で数%から5%以上にまで上昇している企業も少なくありません。これは、獲得コストの増加と、露出競争の激化を如実に示しています。
3. 薄利多売のビジネスモデルの限界
人材派遣業は、派遣料金から派遣社員の賃金や社会保険料、福利厚生費、派遣会社の運営費などを差し引いた「マージン」で成り立っています。このマージン率は、競争が激しいため大幅な引き上げが難しく、薄利多売のビジネスモデルとなっています。
上記の人材確保コストの増加が、薄いマージン率のビジネスモデルに直接的な打撃を与えています。売上を伸ばしても、それ以上にコストが増加すれば、利益は減少し、経営を圧迫する要因となります。
採用コストの内訳は、主に求人広告費(Indeed、求人ボックスなどの運用型広告費)、ダイレクトリクルーティングの利用料、人材紹介サービスへの成功報酬、そして自社の採用担当者の人件費などが挙げられます。これらの費用が、求職者の絶対数不足、他社との競争激化、求職者ニーズの多様化によって、軒並み上昇しているのが現状です。特に、Web広告費はクリック単価の高騰により、費用対効果の悪化が顕著です。
※2:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」より人材派遣・紹介業の傾向を引用。
※3:主要人材派遣会社の公開されている決算情報やIR資料、各種業界レポートから、販促費(販売費及び一般管理費内の広告宣伝費など)の推移や売上高比率の傾向を推計し、記述しています。
プロである派遣会社も苦戦する理由
人材採用のノウハウを持つプロフェッショナルであるはずの人材派遣会社が、なぜこれほどまでに苦戦しているのでしょうか。それは、個社の努力だけでは抗い難い、市場全体の構造的変化と、求職者の価値観の大きな変化が背景にあるためです。
ノウハウだけでは乗り越えられない壁
どんなにノウハウがあっても、市場全体の労働力人口が減少しているため、そもそも獲得できる人材の「パイ」が小さくなっています。これは、プロの採用力を以てしても解決が難しい根本的な問題です。
求職者は、派遣会社が紹介する「案件」だけでなく、その案件を提供する「企業(派遣先)」の文化、働き方、福利厚生、将来性などを以前よりも深く見極めるようになりました。派遣会社は、派遣先の企業ブランディングまでを考慮したマッチングが求められます。
派遣先企業はコスト削減を求めるため、派遣会社間の価格競争が常態化しています。これにより、派遣会社は十分に利益を確保できず、人材確保への投資が滞りがちになる悪循環に陥ります。
採用後も続く課題 – 定着と流動性
人材を確保しても、それが「安定的な労働力」として定着するとは限りません。派遣社員特有の流動性と、現代の求職者心理が絡み合い、採用後も派遣会社は定着の課題に直面します。
派遣社員の定着を阻む要因
特に優秀な派遣社員は、就業中も他社からのスカウトメール(ダイレクトリクルーティングや人材紹介経由)を受け取ることが非常に多いです。ビズリーチなどでは、現在の勤務先にバレずに転職活動ができる機能があるため、派遣元(人材派遣会社)が気づかないうちに、より良い条件の企業へ転職してしまうリスクがあります。
派遣社員は、契約期間満了後の仕事への不安を常に抱えています。これが、より安定した直接雇用への志向や、自身の市場価値を常に試す行動に繋がります。
派遣先企業の文化や人間関係、業務内容とのミスマッチも、早期の契約終了や次の案件への不安に繋がり、定着を阻害します。
人手不足時代に派遣が選ばれにくくなる背景
人材不足が深刻化し、企業が求職者を奪い合う「超売り手市場」となったことで、求職者、特に若年層や専門スキルを持つ人材は、以前にも増して「仕事を選ぶ」立場になりました。この状況は、派遣という働き方にも大きな影響を与えています。
求職者の選択肢の広がりと派遣離れ
人手不足の企業は、優秀な人材を直接雇用するために、正社員としての安定した雇用、高い給与水準、充実した福利厚生、明確なキャリアパスといった魅力的な条件を提示する傾向が強まっています。これにより、求職者は派遣を選ぶよりも、より好条件の直接雇用を選びやすくなりました。
コロナ禍を経て、リモートワークやフレックスタイム制など、正社員でも柔軟な働き方が可能な企業が増えました。これにより、「自由な働き方」を求めて派遣を選ぶニーズが、直接雇用で満たされるケースも増えています。
若年層を中心に、単なる「仕事」ではなく「キャリア形成」を重視する傾向が強まっています。派遣という雇用形態では、長期的なスキルアップや役職への昇進機会が限られると感じる求職者もいるため、キャリア志向の高い人材は直接雇用を選ぶ傾向にあります。
派遣社員の絶対数が不足しているため、登録している派遣社員一人ひとりが複数の派遣会社や直接雇用の選択肢を持っています。これにより、派遣社員はより好条件の案件や企業を選びやすく、既存の派遣先で不満があればすぐに別の選択肢を探す、という流動性の高さも維持されています。
このように、人手不足時代は、求職者にとって仕事を選びやすい環境が広がり、より待遇や安定性の高い雇用形態が選好される傾向にあります。これは、派遣というビジネスモデルが、求職者のニーズ変化に合わせた変革を迫られていることを意味します。
これから企業が取り組むべき戦略
人材派遣会社がこの厳しい時代を生き抜くためには、従来のビジネスモデルだけでは限界があります。企業は、抜本的な戦略転換と、より顧客(派遣社員と派遣先企業)に寄り添ったアプローチが求められます。
上記フローは、人材派遣会社が取るべき戦略を示しています。特に重要なのは、「量」から「質」への転換と、派遣社員と派遣先企業の双方に対する「伴走型」の支援です。
まとめ – 採用難時代を生き抜くために
人材派遣会社の倒産増加は、日本の労働市場が直面する構造的な人手不足と採用競争の激化を如実に物語っています。プロであるはずの派遣会社でさえ、人材確保の困難さ、採用コストの高騰、そして薄利多売のビジネスモデルの限界という三重苦に苦しんでいます。
しかし、これは単なる悲観論ではありません。この危機は、人材派遣業界が「量」から「質」への転換を図り、より高付加価値なサービスを提供するための変革期でもあります。登録者への手厚い育成・定着支援、DXによる業務効率化、そして派遣先企業との強固なパートナーシップの構築が、これからの生存戦略となるでしょう。
本記事は、人材派遣業界が直面する大きな課題の序章にすぎません。次回の記事では、これらの課題を乗り越え、持続可能なビジネスモデルを確立するための、より具体的な戦略と、各社の成功事例に深く踏み込んでいきます。